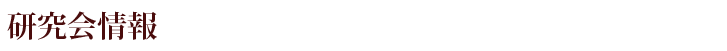このページでは、史学会に寄せられた、歴史学に関連する研究会や学会、講演会、展覧会などの情報をご案内しています。詳細は、それぞれの問い合わせ先にお尋ねください。
皆様からの積極的な情報提供をお待ちしています。
埼玉県立歴史と民俗の博物館 収蔵品展「太平記をよむ」[2026.01.28掲載]
|
日時: |
令和8年1月2日~2月23日 |
|---|---|
|
場所: |
埼玉県立歴史と民俗の博物館 |
|
主催: |
埼玉県立歴史と民俗の博物館 |
|
趣旨説明、プログラムなど: |
収蔵品展「太平記をよむ」の開催について 埼玉県立歴史と民俗の博物館では令和8年1月2日(金)から令和8年2月23日(月・祝)まで、「収蔵品展 太平記をよむ」を開催します。 |
|
問い合わせ先: |
特集展示・広報担当 大見(048-645-8171) |
「異文化交流の世界史」第19回オンライン講演会[2025.12.24掲載]
|
日時: |
2026年2月13日(金)19:30~21:00 |
|---|---|
|
場所: |
オンライン(Zoom) |
|
主催: |
科学研究費基盤研究(A)「近世ユーラシアの宗教アイデンティティ:グローバル多元主義と地域大国主義の相克」(代表:守川知子) |
|
趣旨説明、プログラムなど: |
歴史上、人はどのように他者と邂逅し、交流したのかを検討するにあたり、さまざまな地域や時代の歴史をご専門とされる先生方をお招きして、オンライン(Zoom)による連続講演会「異文化交流の世界史」を開催します。 第19回は下記の要領で行います。
日時:2026年2月13日(金)19:30~21:00 講師:津村 眞輝子先生(古代オリエント博物館館長) テーマ:「銀が動かす古代世界──人と金属の出会いからコインの誕生と発展」
【講師紹介】 専門は考古美術史。ウズベキスタン、シリア、エジプトなどの発掘調査に参加し、出土資料の調査研究を通して、西アジアおよび中央アジアの東西交流、特にコインの研究をしている。編著書に、『世界の金貨と銀貨:コインに刻まれた人間模様』(古代オリエント博物館、2006年)、『古代オリエントの世界』(山川出版社 2009年)、『栄光のペルシア』(山川出版社、2010年)などがある。 *人類が金属を使い始めた約1万年前以来、金属は社会に大きな影響を与えてきました。とくに古代オリエントでは、銀は価値をはかる素材からコインへと発展し、広い地域を結ぶ役割を担います。今回は、出土資料を手がかりに、古代世界を動かした銀の歴史をご紹介いただきます。
申込先: https://forms.gle/xewu9mptrwxz6nj1A *Googleフォームでの申し込みとなります。前日の2月12日正午までに、上記のURLからお申し込みください。 *お申し込みいただいた方へ、前日中に、当日のURL(Zoom)をお送りいたします。 ご講演は45~50分、質疑応答は30~35分と、ディスカッションを重視した時間配分となっております。
【これまでの講演会】 第1回・5月31日(金) 西川杉子先生(東京大学)「ユグノーたちのロンドン」
【今後の予定】 第20回・3月4日(水) 小林和夫先生(早稲田大学) |
|
問い合わせ先: |
tomomo■l.u-tokyo.ac.jp(■を@に変えてください) |
埼玉県立歴史と民俗の博物館 特別展「埼玉の宝物~人々が守り伝えた文化財~」[2026.01.28掲載]
|
日時: |
令和8年3月14日~5月6日 |
|---|---|
|
場所: |
埼玉県立歴史と民俗の博物館 |
|
主催: |
埼玉県立歴史と民俗の博物館 |
|
趣旨説明、プログラムなど: |
埼玉県立歴史と民俗の博物館 特別展開催のお知らせ 平成11 年度以降に新たに指定となった、埼玉県内に所在する国・県指定文化財に関する展覧会です。 展示資料は重要文化財「絹本著色阿弥陀聖衆来迎図」、県指定文化財「小渕観音院 円空仏群」をはじめ、絵画、彫刻、工芸品、典籍、古文書、考古資料、歴史資料など、また作品年代も縄文時代から昭和時代と幅広く紹介します。また、埼玉県の生業がわかる有形民俗文化財やお祭り、行事といった無形民俗文化財も実物資料や映像資料をもとに紹介します。 次世代に継承すべき「埼玉の宝物」をとおして、文化財の魅力に迫ります。 |
|
問い合わせ先: |
特集展示・広報担当(048-645-8171) |
日本学士院 クリス・ウィッカム客員選定記念講演会について[2026.02.13掲載]
|
日時: |
2026年3月19日(木)午後3時30分~5時30分 |
|---|---|
|
場所: |
日本学士院およびオンライン (ハイブリッド開催) |
|
主催: |
日本学士院 |
|
趣旨説明、プログラムなど: |
日本学士院では、わが国における学術の発達に関し特別に功労のあった外国人研究者を日本学士院客員として選定しています。 このたび、西洋中世史家のクリス・ウィッカム教授(英国学士院会員、オクスフォード大学名誉教授)を本院客員に選定したことを記念し、 講演者:クリス・ウィッカム客員(Prof. Chris Wickham)
|
|
問い合わせ先: |
日本学士院事務室 gksympo■mext.go.jp(■を@に変えてください) |
総合女性史学会2025年度大会[2026.02.13掲載]
|
日時: |
2026年3月21日(土)11:00~16:35(予定) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
場所: |
昭和女子大学 7号館6S03 |
||||||||||||
|
主催: |
総合女性史学会 |
||||||||||||
|
趣旨説明、プログラムなど: |
|
||||||||||||
|
問い合わせ先: |
jimukyoku■sogojoseishi.com(■を@に変えてください) |
||||||||||||