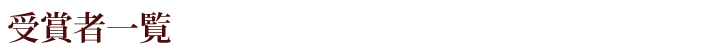|
受賞者 |
小西 正紘 氏 |
|
|
受賞論文 |
「一九世紀半ばのイギリスにおける政治講演会 ――穀物法撤廃運動の事例から――」 『史学雑誌』第133編第4号(2024年4月発行)掲載 |
|
|
受賞者略歴 |
(所 属)東京大学大学院人文社会系研究科 西洋史学専門分野 助教 (主な業績)"Free Trade without Words: Popular Public Rituals and Corn Law Repeal in the Early 1840s," History, vol. 108, no. 379-380 (2023) |
|
|
選考理由 小西正紘氏の論考は、19世紀半ばのイギリスにおいて、反穀物法同盟が雇い入れた巡歴講師たちが全国各地で展開した講演活動を分析することにより、民衆がナショナルな政治的課題に参与していく過程を明らかにするものである。 |
||
第12回史学会賞
|
このたび史学会では史学会賞の選考を行い、以下のとおり第12回史学会賞受賞者が決定いたしました。 |
|
受賞者 |
谷本 隆之 氏 |
|
|
受賞論文 |
「戦国期京都の座と権利」 『史学雑誌』第133編第10号(2024年10月発行)掲載 |
|
|
受賞者略歴 |
(所 属)東京大学史料編纂所 助教 |
|
|
選考理由 谷本隆之氏の論考は、日本中世の商人組織として知られる座について、素材として京都の長坂口紺灰問屋座を取り上げ、緻密な史料分析によって、室町期から戦国期にかけての商人の権利の変容と、戦国期の座の成立との関係を論じたものである。 以上の理由から、選考委員会は本論文を第12回史学会賞にふさわしい優れた論考と評価するものである。
|
||
第11回史学会賞
このたび史学会では史学会賞の選考を行い、以下のとおり第11回史学会賞受賞者が決定いたしました。
2024年11月9日(土)に授賞式が行われました。
|
受賞者 |
渡部 亮 氏 |
|
|
受賞論文 |
「昭和新党運動の重層的展開 |
|
|
受賞者略歴 |
(所 属) (主な業績) |
成蹊大学文学部現代社会学科助教 「占領期社会党の民主戦線運動 |
|
選考理由 渡部亮氏の論考は、政党の解散と大政翼賛会の成立に帰結する1940年の近衛新体制運動の背景を、とりわけこの運動を強力におしすすめた社会大衆党(以下、社大党)の構想と、同党の中央と地方支部との関係に注目しながら論じたものである。 |
||
第10回史学会賞
このたび史学会では史学会賞の選考を行い、以下のとおり第10回史学会賞受賞者が決定いたしました。
2023年11月11日(土)に授賞式が行われました。
|
受賞者 |
トーマス・バレット 氏 |
|
|
受賞論文 |
「「D.B.マッカーティと「琉球処分」問題 |
|
|
受賞者略歴 |
(所 属) (主な業績) |
ケンブリッジ大学アジア・中東学部ポストドクトラルフェロー ”Un pont entre les mondes: les diplomaties de l’ombre |
|
選考理由 トーマス・バレット氏の論考は、在外公館員の主体性という新たな分析視角から「琉球処分」問題を論じたものである。1877年から1880年にかけて駐日清国公使館に勤務したアメリカ人D・B・マッカーティの私的活動に注目し、それが琉球をめぐる日清間の外交交渉に与えた影響を明らかにしようとする。 |
||
第9回史学会賞
このたび史学会では史学会賞の選考を行い、以下のとおり第9回史学会賞受賞者が決定いたしました。
2022年11月12日(土)に授賞式が行われました。
|
受賞者 |
村田 優樹 氏 |
|
|
受賞論文 |
「革命期ロシアのウクライナ問題と近世ヘトマン領 ――過ぎ去った自治と来るべき自治――」 『史学雑誌』第130編7号(2021年7月発行)掲載 |
|
|
受賞者略歴 |
(所 属) ウィーン大学歴史文化学部博士課程 (主な業績)"Multiple Paths to Autonomy: Moderate Ukrainians in Revolutionary Petrograd," Kritika, vol. 22, no. 2 (2021). |
|
|
選考理由 村田優樹氏の論考は、ウクライナの近世ヘトマン領の歴史的意義を考察した帝政末期ロシアの歴史家フルシェフスキーと法学者ノリデの学問研究と政治的実践活動を対比して分析することを通じて、「歴史研究・国制論・実践政治」の相互関係を明らかにし、近代ロシア国家構造におけるウクライナ問題の重層的特徴の解明に新たな視点を提示した。 歴史学と国法学という異なる問題関心から近世ヘトマン領研究を進めたフルシェフスキーとノリデの二人は、ロシア国家に組み込まれた近世ヘトマン領に地域自治の存在を見出した。しかし他方で二人は、ロシア帝国内部の地域自治原理の評価については大きな相違を示し、ロシア革命期に顕在化したウクライナ自治要求をめぐっては対立する立場を示すことになる。この経緯を著者は、二人の著述の精緻な読解によって鮮やかに描き出し、ロシア帝国においてウクライナ問題が議論された複雑な様相を明らかにした。 未公刊史料を博捜して歴史を再構成する近年のロシア史研究に多く見られる方法とは異なり、著者は、急速に進展したナショナリズム研究・帝国史研究の成果をふまえて同時代の基本文献を現代的な問題関心から多角的に分析することで、二人の学問的主張と政治的実践活動との関連性の解明に大いに貢献した。時に明確さを欠く表現には改善の余地もあるものの、帝国内の地域自治を歴史的に考察した知識人が現実の自治問題に示した相対する見解を剔出した本論考は、歴史認識と現実政治との関わりを考えるうえで、またウクライナ民族問題だけでなく近代諸帝国の民族問題を比較考察するうえでも、新たな可能性をひらく展望の広さを有している。 以上の理由から、選考委員会は本論文を第9回史学会賞にふさわしい優れた論考と評価するものである。 |
||
第8回史学会賞
このたび史学会では史学会賞の選考を行い、以下のとおり第8回史学会賞受賞者が決定いたしました。
2021年12月13日(月)に授賞式が行われました。
|
受賞者 |
袁 甲幸 氏 |
|
|
受賞論文 |
「明治前期の府県庁「会議」 |
|
|
受賞者略歴 |
(所 属) (主な業績) |
早稲田大学総合人文科学研究センター助手 「三新法体制における府県「公権」の形成」 「地方税寄付収入に対する府県会議定権の変遷」 |
|
選考理由 袁甲幸氏の論考は、1880年前後の府県庁で、高級幹部ではなく、数的に大多数を占めていた属官たちによって、「公論」形成の場としての会議が開かれていたことを明らかにした。 袁氏は多くの府県の史料を調査して、全国的な制度では定められていないこの種の会議が、1875年の地方官会議を契機に「官民共議」の場であった地方民会から議員としての府県庁官吏が排除されたことに対応して、民会に出席する官吏が説明する県庁の方針を定める必要と、府県庁内部での対等な議論で「公論」を形成しようとする属官たちの意志により、さまざまな府県で開かれるようになったことを示した。そして、まとまった史料が残る岩手県の例を検討し、決定権は県令にあるが、各課署の正副長と課内で毎月選出される議員たちが、住民が選ぶ府県会の議員が地元の利害や負担能力を反映するのに対し、府県会での審議内容も見識に組み込んだ自分たちの「衆議」こそが「公論」を形成すると考えて議論し、予算原案を修正して県会との紛議を防ぐなど、円滑な統治をもたらしたことを指摘した。そして、このような会議は、官僚制が発達し庁内の階級差が拡大し、専門性が深まる1890年前後には見られなくなるとする。 幕末以来の「公論」や明治の地方制度を巡る研究の進展を踏まえつつ、その両者を貫く新たな視角を示し、この時期には他地域出身の県令が県会と対立、妥協しながら個性的に地方統治を進めたとする理解を、根本的に再考させる成果である。この研究で新たに示された、「公論」を形成すべく中下級官吏の会議が幅広く行なわれていたという事実は、この時代に「公論」意識が根強く存在し、行政に反映されていたことを示す点で日本近代史に新たな知見を加え、議会以外の場での議論に注目すべきでないことを示す点で、地域や時代を越えた意義を持つ。 以上の理由から、選考委員会は本論文を第8回史学会賞にふさわしい優れた論考と評価するものである。 |
||
第7回史学会賞
このたび史学会では史学会賞の選考を行い、以下のとおり第7回史学会賞受賞者が決定いたしました。
2020年12月8日(火)に授賞式が行われました。
|
受賞者 |
付 晨晨 氏 |
|
|
受賞論文 |
「斉梁類書の誕生 |
|
|
受賞者略歴 |
(最終学歴) (主な業績) |
東京大学大学院人文社会系研究科博士課程満期退学 「『藝文類聚』から見た初期類書の性格」 |
|
選考理由 付晨晨氏の論考は、初期類書の発展過程を分析して斉梁期にその画期を見出すとともに、初期類書の斉梁類書への転換の背景に、皇帝が抱える知識整理の必要性と、寒門士族がもつ自己の文化的価値向上の思惑との見事な一致を見出したものである。 すなわち、著者は、『皇覧』を始祖とする初期類書の系譜を、唐代の『華林遍略』に至るまで詳細に辿り、それぞれの類書に記載された内容を比較検討したうえで、初期類書の発展を南朝(420―589)の斉梁期に見出す。そのうえで、斉梁類書の出現の歴史的意義を、知識の面での新時代の幕開けを告げるところに見出そうとする。隋唐時代以前の類書が全て散逸している中で、著者は、唐人の斉梁類書に対する議論と、斉梁類書と直接に継承関係をもつ唐代類書とを検討の素材として、斉梁類書の性格に迫っているが、限定された史料の丹念な収集と、それらを多角的に分析して着実に議論を進めていく研究手法は、史料の限られた古代史の研究方法として範とされるべきものである。 また、著者は、斉梁期の類書編纂の背景に、漢代以前の知識を主とする『皇覧』から、魏晋の知識を「典故化」するものへとの類書の性格の変化を見出し、あわせてこのことが、当時の寒門士人による、朝廷に書籍や知識を提供することで彼らの有する文化的資源をより価値あるものにしようとする志向によるものであることも明らかにしている。類書編纂の有り様の変化という文化史的現象の指摘に留まらず、それが、類書編纂に当たった寒門士人の成長と絡み合った結果であるとの見通しを得られたことは、今後、南朝の政治や社会の歴史を論じていく上での本論考の研究史への大きな貢献であるということもできる。 以上の理由から、選考委員会は本論文を第7回史学会賞にふさわしい優れた論考と評価するものである。 |
||
第6回史学会賞
このたび史学会では史学会賞の選考を行い、以下のとおり第6回史学会賞受賞者が決定いたしました。
2019年11月9日(土)に開催された第117回史学会大会にて授賞式が行われました。
|
受賞者 |
殷 晴 氏 |
|
|
受賞論文 |
「清代における邸報の発行と流通 |
|
|
受賞者略歴 |
(所 属) (主な業績) |
東京大学大学院人文社会系研究科博士課程学生 「提塘からみた清朝中央と地方の情報伝達」 |
|
選考理由 本論文は、清代の中央政府の情報が邸報をとおして各地に伝播していく過程を、中央政府の書吏、出版業者の活動から検討した力作である。従来あまり関心が払われなかった中央の情報の伝わり方に着目することで、清朝における中央と地方、官と民の関係を考えるための貴重な材料を提供する。 邸報は、皇帝への上奏文や謁見した官僚さらに各部局の報告などからなる。書吏によって記された邸報が、営利目的の印刷業者(「小報房」)によって印刷され、それを各省の駐京提塘が購入して、3日に1回の頻度で北京から州都へ邸報を発送した。邸報は州都の高級官僚に届けられるとともに、さらに複写・印刷されて地方官や民間人にも販売されたことが明らかにされる。また書吏が、邸報の配達に参入する場合もあった。邸報には、各版本間に内容の相違があり、また上奏文の取捨選択のし方にも差異があったにもかかわらず、中央政府は書吏の記述に誤りのない限り基本的に干渉せず、一時期を除き印刷業者も監督しなかった。清朝の国家統合を考える上で、興味深い慣行が提示される。 本論文は、清朝の情報伝達の変化にも目配りがされている。情報管理の強化をはかるため中央政府は、乾隆後期に印刷業者として駐京提塘が共同で運営する公慎堂を設立させた。しかし、資金難のため、道光年間に個人経営の印刷業者が復活したことが示される。20世紀になると、情報伝達の不統一性が問題になり、中央政府自らが情報を発信するようになる。さらに日清戦争以降には、新聞や雑誌が全国的に普及する。ただし、これらの媒体でも、書吏が情報源として重宝された慣行が明らかになる。 論点の提示の仕方は明快で、史料にもとづく実証も行き届いている。清朝をはじめ前近代の王国史研究に新たな展望を開く秀作として、本論文は史学会賞にふさわしい作品であると判断した。 |
||
第5回史学会賞
このたび史学会では史学会賞の選考を行い、以下のとおり第5回史学会賞受賞者が決定いたしました。
2018年11月24(土)に開催された第116回史学会大会にて授賞式が行われました。
|
受賞者 |
前野 利衣 氏 |
|
|
受賞論文 |
「十七世紀後半ハルハ=モンゴルの権力構造とその淵源 |
|
|
受賞者略歴 |
(所 属) (主な業績) |
東京大学大学院総合文化研究科地域文化研究専攻博士課程学生 「ジノンの地位とその継承過程からみた17世紀ハルハ右翼の三核構造」 |
|
選考理由 前野利衣氏の論考は、17世紀後半のハルハ゠モンゴルの権力構造の特徴を、右翼のチベット仏教転生僧に着目することによって浮き彫りにしたものである。 本論考がもたらした具体的な知見は以下の三点である。第一は、近親者で聖俗両界の頂点を占めて共同で統治する形態がハルハ右翼に生まれていたことを解明した点である。第二は、このような統治形態がハルハ右翼のみならず、全ハルハ゠モンゴルに共通するものであったことを明らかにした点である。第三は、ハルハ゠モンゴルにおける聖俗の権力構造が、チベット仏教影響下にある諸地域にまで広がっていたことを指摘した点である。 本論文の際立った特長は、漢文、チベット語、モンゴル語、ロシア語文献など多言語・多系統の資料を駆使していることである。これによって、従来史料的な制約によって解明が遅れていたハルハ右翼に関する実証的研究成果が得られたことに加え、ハルハ゠モンゴルの権力構造についても新たな理解が提示されている。また、世俗権力と宗教的権威との拮抗・対抗関係について西洋の事例との比較研究が展望されている点は、研究のスケールに大きな幅を与えており、論文の論理構成や叙述も申し分ないものだといえる。 著者が有する多言語能力をブラッシュアップすることにより個々の史料の読み込みに深みを与えつつ、こうした事例が全ユーラシア史にもつ意味、様々な比較研究の中で見えてくるもの、といった大きな問題意識の中で議論が展開されることで、学界に大きな刺激を与えることが期待される。 以上の理由から、選考委員会は本論文を第5回史学会賞にふさわしい優れた業績と評価するものである。 |
||
第4回史学会賞
このたび史学会では史学会賞の選考を行い、以下のとおり第4回史学会賞受賞者が決定いたしました。
2017年11月11(土)に開催された第115回史学会大会にて授賞式が行われました。
|
受賞者 |
紺谷 由紀 氏 |
|
|
受賞論文 |
「ローマ法における去勢 |
|
|
受賞者略歴 |
(所 属) (主な業績) |
東京大学大学院人文社会系研究科博士課程学生 「コンスタンティウス2世治世(337-361年)における聖室長官エウセビウスの位置付け――宮廷宦官の人的関係に関する一考察――」 |
|
選考理由 紺谷由紀氏の論文は、後期ローマ帝政期において宮廷機構の内部で用いられていた宦官などの去勢者という存在をローマ法がどのように位置づけていたかを1世紀から6世紀の法史料の網羅的分析を通じて考察したものである。 |
||
第3回史学会賞

このたび史学会では史学会賞の選考を行い、以下のとおり第3回史学会賞受賞者が決定いたしました。
2016年11月12日(土)に開催されました第114回史学会大会総会にて、授賞式が行われました。
|
受賞者 |
藤波 伸嘉 氏 |
|
|
受賞論文 |
「ババンザーデ・イスマイル・ハックのオスマン国制論 |
|
|
受賞者略歴 |
(現 職) |
津田塾大学学芸学部国際関係学科准教授 『オスマン帝国と立憲政 |
|
選考理由 イスラーム圏の国制論においては、イスラームといういわば特殊な要因が前面に出る場合が多く、近代的諸価値への対抗が強調される傾向が強い。本論文は、オスマン帝国末期の法学者・政治家であったババンザーデ・イスマイル・ハック(1876-1913)の著作『国法』を主に取り上げ、近代的な意味での主権や立憲制を踏まえて眼前のオスマン国制を論じた全く異なった思想潮流を提示したものである。 |
||
第2回史学会賞

このたび史学会では史学会賞の選考を行い、以下のとおり第2回史学会賞受賞者が決定いたしました。
2015年11月14日(土)に開催されました第113回史学会大会総会にて、授賞式が行われました。
|
受賞者 |
吉井 文美 氏 |
|
|
受賞論文 |
「「満洲国」創出と門戸開放原則の変容 |
|
|
受賞者略歴 |
(現 職) |
山形大学人文学部講師 |
|
選考理由 1931年の「満洲事変」によって、中国東北部が「満洲国」の行政下に置かれて以後、英米を始めとする諸外国は、中国との間で保有していた「条約上の権利」がどのような影響を蒙るのかについて、重大な関心を寄せていた。日本外務省は、当初1922年のワシントン会議で締結された9か国条約の遵守を表明していたが、「満洲」の実質的な植民地化という、軍部以下日本政府の本音に押されて、「満洲国」不承認の国には門戸開放原則を適用しないとの態度をちらつかせるなど、9か国条約の実質的空洞化をはかった。 |
||
第1回史学会賞
 このたび史学会では史学会賞の選考を行い、以下のお2方が第1回史学会賞受賞者に決定いたしました。
このたび史学会では史学会賞の選考を行い、以下のお2方が第1回史学会賞受賞者に決定いたしました。
2014年11月8日(土)に開催されました第112回史学会大会総会において受賞者が発表され、併せて授賞式が行われました。
|
受賞者 |
後藤 はる美 氏 |
|
|
受賞論文 |
「17世紀イングランド北部における法廷と地域秩序 |
|
|
受賞者略歴 |
(現 職) |
東洋大学文学部史学科講師 |
|
選考理由 後藤はる美氏の論文は、17世紀初頭のイングランド北部ヨークシャ州における社会秩序の形成過程を、地域エリートたちが繰り広げた政治的・文化的なヘゲモニー争いに注目することにより解明したものである。 |
||
|
受賞者 |
城地 孝 氏 |
|
|
受賞論文 |
「明嘉靖馬市考」 |
|
|
受賞者略歴 |
(現 職) |
京都大学人文科学研究所非常勤研究員 |
|
選考理由 城地孝氏は、明代の嘉靖・隆慶年間(1522-66、67-72年)を対象とする政治史研究で研鑽を積み重ねており、本論文はその一環に位置づけられる。なお本論文を含む2004年以来の研究成果は、著書『長城と北京の朝政』にまとめられている。 |
||