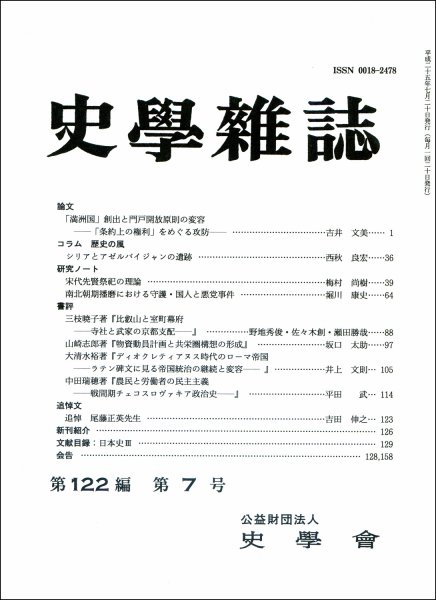122編第12号
|
論文 |
| |||
|---|---|---|---|---|
|
大宝律令の制定と「蕃」「夷」 |
|
大高 広和 |
1(1985) |
|
|
研究ノート | |||
|---|---|---|---|
|
足利一門再考――「足利的秩序」とその崩壊―― |
|
谷口 勇太 |
35(2019) |
|
南京国民政府時期の上海における刑事裁判 |
|
久保茉莉子 |
58(2042) |
|
書評 | |||
|
芳之内圭著『日本古代の内裏運営機構』 |
仁藤 敦史 | 83(2067) | |
|
大門正克編著 |
坂口 正彦 | 87(2071) | |
|
村上宏昭著 |
田野 大輔 | 93(2077) | |
|
新刊紹介 | |||
|
江田郁夫・簗瀬大輔編『北関東の戦国時代』 |
木下 聡 |
98(2082) |
|
|
森 正人・稲葉継陽編 |
金子 拓 |
99(2083) |
|
|
国税庁税務大学校税務情報センター租税史料室編著 |
中西 啓太 |
101(2085) |
|
|
平㔟隆郎著『「八紘」とは何か』(東京大學東洋文化研究所報告) |
鈴木 舞 |
101(2085) |
|
|
岩崎育夫著『物語 シンガポールの歴史 |
東條 哲郎 |
103(2087) |
|
|
間野英二著『バーブル――ムガル帝国の創設者――』 |
二宮 文子 |
104(2088) |
|
|
伊藤航多・佐藤繭香・菅 靖子編著 |
八谷 舞 |
105(2089) |
|
|
文献目録 | |||
|
日本史Ⅵ |
106(2090) |
||
|
会告 | |||
|
141(2125) |
|||
|
史学雑誌第122編総目次 | |||
122編第11号
|
論文 |
| |||
|---|---|---|---|---|
|
日中戦争時期中国占領地における将来構想 |
|
関 智英 |
1(1823) |
|
|
コラム 歴史の風 | ||||
|
高松塚古墳壁画の特別公開 |
早乙女雅博 |
28(1850) |
||
|
研究ノート | |||
|---|---|---|---|
|
唐代の賵賻制度について――唐喪葬令を中心として―― |
|
劉 可維 |
31(1853) |
|
幕府海軍における「業前」と身分 |
|
水上たかね |
54(1876) |
|
書評 | |||
|
服部一隆著『班田収受法の復原的研究』 |
坂上 康俊 | 87(1747) | |
|
渡邉俊著『中世社会の刑罰と法観念』 |
小瀬 玄士 | 95(1755) | |
|
中野忠・道重一郎・唐澤達之編 |
岩間 俊彦 | 96(1918) | |
|
藤原辰史著『ナチスのキッチン――「食べること」の環境史――』 |
小野寺拓也 | 105(1927) | |
|
新刊紹介 | |||
|
阿部泰郎著『中世日本の宗教テクスト体系』 |
藤井 雅子 |
115(1937) |
|
|
中野目徹・熊本史雄編 |
国分 航士 |
116(1938) |
|
|
栄新江著/高田時雄監訳/西村陽子訳『敦煌の民族と東西交流』 |
吉田 愛 |
117(1939) |
|
|
アブデュルレシト・イブラヒム著/小松香織・小松久男訳 |
山﨑 典子 |
118(1940) |
|
|
本村凌二編著『ローマ帝国と地中海文明を歩く』 |
丸亀 裕司 |
120(1942) |
|
|
文献目録 | |||
|
日本史Ⅴ |
121(1943) |
||
122編第10号
|
論文 |
| |||
|---|---|---|---|---|
|
ティムールの冬営地と帝国統治・首都圏 |
|
川口 琢司 |
1(1661) |
|
|
研究ノート | |||
|---|---|---|---|
|
日露戦後における内務省地方局市町村課と地方行政機構 |
|
中西 啓太 |
39(1699) |
|
戦前における金森徳次郎の憲法解釈論 |
|
霜村 光寿 |
61(1721) |
|
書評 | |||
|
藤本頼人著『中世の河海と地域社会』 |
綿貫 友子 | 87(1747) | |
|
三鬼清一郎著『織豊期の国家と秩序』 |
深谷 幸治 | 95(1755) | |
|
吉田伸之著『伝統都市・江戸』 |
横山百合子 | 103(1763) | |
|
紀旭峰著『大正期台湾人の「日本留学」研究』 |
洪 郁如 | 113(1773) | |
|
新刊紹介 | |||
|
中島楽章・伊藤幸司編『寧波と博多』 |
高木 久史 |
120(1780) |
|
|
小原仁編『『玉葉』を読む――九条兼実とその時代――』 |
山本みなみ |
121(1781) |
|
|
奥中康人著『幕末鼓笛隊――土着化する西洋音楽――』 |
淺川 道夫 |
122(1782) |
|
|
諫早直人著『海を渡った騎馬文化――馬具からみた古代東北アジア――』 |
板橋 暁子 |
123(1783) |
|
|
森下嘉之著『近代チェコ住宅社会史――新国家の形成と社会構想――』 |
芦部 彰 |
124(1784) |
|
|
文献目録 | |||
|
東洋史Ⅲ |
126(1786) |
||
122編第9号
|
論文 |
| |||
|---|---|---|---|---|
|
平沼騏一郎内閣運動と海軍 |
|
手嶋 泰伸 |
1(1507) |
|
|
コラム 歴史の風 | ||||
|
第一次世界大戦とソビエト連邦の成立について |
石井 規衛 |
33(1539) |
||
|
研究ノート | |||
|---|---|---|---|
|
突厥第二可汗国の内部対立――古チベット語文書(P.t.1283)にみえる |
|
齊藤 茂雄 |
36(1542) |
|
江戸幕府所司代赴任時の老中上京について |
|
荒木 裕行 |
62(1568) |
|
書評 | |||
|
上村喜久子著『尾張の荘園・国衙領と熱田社』 |
小嶋 教寛 | 84(1590) | |
|
勝俣鎮夫著『中世社会の基層をさぐる』 |
中澤 克昭 | 91(1597) | |
|
石井寛治著『帝国主義日本の対外戦略』 |
松浦 正孝 | 100(1606) | |
|
新刊紹介 | |||
|
吉田歓著『古代の都はどうつくられたか――中国・日本・朝鮮・渤海――』 |
角山 典幸 |
110(1616) |
|
|
国立歴史民俗博物館・玉井哲雄編『アジアからみる日本都市史』 |
松田 法子 |
111(1617) |
|
|
五味文彦著『鴨長明伝』 |
長村 祥知 |
112(1618) |
|
|
北野剛著『明治・大正期の日本の満蒙政策史研究』 |
白田 拓郎 |
113(1619) |
|
|
金子修一主編『大唐元陵儀注新釈』 |
山下 洋平 |
114(1620) |
|
|
中国ムスリム研究会編『中国のムスリムを知るための60章』 |
上出徳太郎 |
116(1622) |
|
|
長沢栄治著『エジプトの自画像――ナイルの思想と地域研究――』 |
西舘 康平 |
117(1623) |
|
|
文献目録 | |||
|
西洋史Ⅲ |
119(1625) |
||
|
会告 | |||
|
118(1624) |
|||
122編第8号
|
論文 |
| |||
|---|---|---|---|---|
|
国人領主の在京活動 |
|
吉永 隆記 |
1(1345) |
|
|
研究ノート | |||
|---|---|---|---|
|
九条家の相続にみる「処分状」の変遷と衰退 |
|
巽 昌子 |
30(1374) |
|
昭和期における都市地縁集団の再編と町内会連合会 |
|
伊藤 久志 |
57(1401) |
|
書評 | |||
|
大山喬平著『日本中世のムラと神々』 |
服部 英雄 | 80(1424) | |
|
小林和幸著『谷 干城――憂国の明治人――』 |
中野目 徹 | 89(1433) | |
|
北原淳著『タイ近代土地・森林政策史研究』 |
佐藤 仁 | 94(1438) | |
|
貴堂嘉之著『アメリカ合衆国と中国人移民 |
馬 暁華 | 104(1438) | |
|
新刊紹介 | |||
|
湯浅治久著『蒙古合戦と鎌倉幕府の滅亡』 |
田中 大喜 |
111(1455) |
|
|
麻田雅文著『中東鉄道経営史』 |
吉井 文美 |
112(1456) |
|
|
小野泰著『宋代の水利政策と地域社会』 |
宇都宮美生 |
113(1457) |
|
|
永原陽子編『生まれる歴史、創られる歴史 |
小林 理修 |
114(1458) |
|
|
北村暁夫/伊藤武編著『近代イタリアの歴史 |
大西 克典 |
115(1459) |
|
|
文献目録 | |||
|
日本史Ⅳ |
117(1461) |
||
122編第7号
|
論文 |
| |||
|---|---|---|---|---|
|
「満洲国」創出と門戸開放原則の変容 |
|
吉井 文美 |
1(1183) |
|
|
コラム 歴史の風 | ||||
|
シリアとアゼルバイジャンの遺跡 |
西秋 良宏 |
36(1218) |
||
|
研究ノート | |||
|---|---|---|---|
|
宋代先賢祭祀の理論 |
|
梅村 尚樹 |
39(1221) |
|
南北朝期播磨における守護・国人と悪党事件 |
|
堀川 康史 |
64(1246) |
|
書評 | |||
|
三枝暁子著『比叡山と室町幕府 |
野地秀俊・佐々木創・瀬田勝哉 | 88(1270) | |
|
山崎志郎著『物資動員計画と共栄圏構想の形成』 |
坂口 太助 | 97(1279) | |
|
大清水裕著『ディオクレティアヌス時代のローマ帝国 |
井上 文則 | 105(1287) | |
|
中田瑞穂著『農民と労働者の民主主義 |
平田 武 | 114(1296) | |
|
追悼文 | |||
|
追悼 尾藤正英先生 |
吉田 伸之 |
123(1305) |
|
|
新刊紹介 | |||
|
熊本近代史研究会『第六師団と軍都熊本』 |
一ノ瀬俊也 |
126(1308) |
|
|
森本淳著『三国軍制と長沙呉簡』 |
大原 信正 |
127(1309) |
|
|
文献目録 | |||
|
日本史Ⅲ |
129(1311) |
||
|
会告 | |||
|
128,158(1310,1340) |
|||
122編第6号
|
論文 | |||
|---|---|---|---|
|
中世の葬送と遺体移送 |
|
島津 毅 |
1(1029) |
|
研究ノート | |||
|
下級官人と月借銭 |
|
市川 理恵 |
34(1062) |
|
研究動向 | |||
|
オスマンとローマ――近代バルカン史学史再考―― |
藤波 伸嘉 |
55(1083) |
|
|
書評 | |||
|
庄司俊作著『日本の村落と主体形成――協同と自治――』 |
坂口 正彦 | 81(1109) | |
|
平田茂樹著『宋代政治構造研究』 |
小林 晃 | 87(1115) | |
|
岡元司著『宋代沿海地域社会史研究――ネットワークと地域文化――』 |
小島 毅 | 96(1124) | |
|
篠原琢・中澤達哉編 |
大津留 厚 | 105(1133) | |
|
新刊紹介 | |||
|
刈部直・黒住真・佐藤弘夫・末木文美士・田尻祐一郎編 |
小原 仁 |
111(1139) |
|
|
塚本学著『塚本明毅――今や時は過ぎ、報国はただ文にあり――』 |
水上たかね |
113(1141) |
|
|
三崎良章著『五胡十六国――中国史上の民族大移動――』〔新訂版〕 |
峰雪 幸人 |
114(1142) |
|
|
高橋文治著『モンゴル時代道教文書の研究』 |
李 龢書 |
115(1143) |
|
|
深町英夫編訳『孫文革命文集』(岩波文庫) |
吉澤誠一郎 |
116(1144) |
|
|
窪田順平監修/承志編『中央ユーラシア環境史 2 国境の出現』 |
上出徳太郎 |
117(1145) |
|
|
窪田順平監修/渡邊三津子編 |
植田 暁 |
118(1146) |
|
|
ゲッツ・アリー著/芝健介訳 |
若林美佐知 |
119(1147) |
|
|
文献目録 | |||
|
東洋史Ⅱ |
121(1149) |
||
|
会告 | |||
|
110(1138) |
|||
122編第5号 回顧と展望
|
総説 | ||
|---|---|---|
|
小松 久男 |
1(613) |
|
|
歴史理論 | ||
|
加藤 陽子 |
6(618) |
|
|
日本 | ||
|
考 古 |
山岡 拓也 安達 香織 小林 青樹 太田 宏明 石神 裕之 |
11(623) |
|
古 代 |
吉村 武彦 加藤 友康 大川原竜一 須永 忍 中村 友一 |
38(650) |
|
中 世 |
美川 圭 佐古 愛己 坂口 太郎 花田 卓司 竹井 英文 |
73(685) |
|
近 世 |
高埜 利彦 牧原 成征 小宮山敏和 吉成 香澄 高橋 博 |
107(719) |
|
近現代 |
中西 聡 奈良 勝司 中元 崇智 谷口 裕信 田浦 雅徳 |
147(759) |
|
東アジア | |||
|---|---|---|---|
|
中 国 |
|||
|
殷・周・春秋 |
鈴木 舞 |
191(803) |
|
|
戦国・秦漢 |
渡邉 将智 |
197(809) |
|
|
魏晋南北朝 |
津田 資久 |
203(815) |
|
|
隋・唐 |
江川 式部 |
210(822) |
|
|
五代・宋・元 |
水越 知 |
216(828) |
|
|
明・清 |
城地 孝 |
223(835) |
|
|
近代 |
宮原 佳昭 |
231(843) |
|
|
現代 |
島田 美和 |
237(849) |
|
|
台湾 |
若松 大祐 |
244(856) |
|
|
朝 鮮 |
赤羽目匡由 鈴木 開 酒井 裕美 |
246(858) |
|
|
内陸アジア | ||
|---|---|---|
|
佐藤 貴保 橘 誠 |
257(869) |
|
|
東南アジア | ||
|
山口 元樹 |
267(879) |
|
|
南アジア | ||
|
小川 道大 三瀬 利之 |
274(886) |
|
|
西アジア・北アフリカ | ||
|
大城 道則 長谷川修一 小笠原弘幸 高橋 圭 |
282(894) |
|
|
アフリカ | ||
|
眞城 百華 |
299(911) |
|
|
ヨーロッパ | |||
|---|---|---|---|
|
古 代 |
|||
|
ギリシア |
齋藤 貴弘 |
303(915) |
|
|
ローマ |
田中 創 |
307(919) |
|
|
中 世 |
|||
|
一般 |
阿部 俊大 |
311(923) |
|
|
西欧・南欧 |
阿部 俊大 |
312(924) |
|
|
中東欧・北欧 |
池田 利昭 |
317(929) |
|
|
イギリス |
上野 未央 |
321(933) |
|
|
ロシア・ビザンツ |
平野 智洋 |
325(937) |
|
|
近 代 |
|||
|
一般 |
小山 哲 |
327(939) |
|
|
イギリス |
勝田 俊輔 |
329(941) |
|
|
フランス |
松嶌 明男 |
336(948) |
|
|
ドイツ・スイス・ネーデルラント |
鈴木 直志 |
343(955) |
|
|
ロシア・東欧・北欧 |
青島 陽子 |
349(961) |
|
|
南欧 |
山手 昌樹 |
354(966) |
|
|
現 代 |
|||
|
一般 |
足立 芳宏 |
358(970) |
|
|
イギリス |
小川 浩之 |
360(972) |
|
|
フランス |
工藤 晶人 |
365(977) |
|
|
ドイツ・スイス・ネーデルラント |
北村 陽子 |
368(980) |
|
|
ロシア・東欧・北欧 |
後藤 正憲 |
375(987) |
|
|
アメリカ | |||
|
北アメリカ |
兼子 歩 高田 馨里 |
381(993) |
|
|
ラテン・アメリカ |
井上 幸孝 |
389(1001) |
|
|
編集後記 | |||
|
395(1007) |
|||
|
文献目録 | |||
|
西洋史II |
395(1007) |
||
|
会告 | |||
|
256,380,416 |
|||
122編第4号
|
論文 | ||
|---|---|---|
|
鎌倉後期・建武政権期の大覚寺統と大覚寺門跡 |
坂口 太郎 |
1(459) |
|
研究ノート | ||
|
大蔵省預金部資金の地方還元と地方金融ルートの編成 |
田中 光 |
40(498) |
|
書評 | ||
|
村井良介著『戦国大名権力構造の研究』 |
渡辺 勝巳 |
66(524) |
|
近藤一成著『宋代中國科擧社會の研究』(汲古叢書 83) |
平田 茂樹 |
74(532) |
|
箱田恵子著『外交官の誕生 |
青山 治世 |
81(539) |
|
木畑洋一・秋田茂編著『近代イギリスの歴史 |
金澤 周作 |
91(549) |
|
若尾祐司・本田宏編『反核から脱原発へ |
村山 聡 |
97(555) |
|
新刊紹介 | ||
|
小野正敏・五味文彦・萩原三雄編『一遍聖絵を歩く |
黒嶋 敏 |
106(564) |
|
早島大祐著『足軽の誕生――室町時代の光と影――』 |
酒井 紀美 |
107(565) |
|
片山慶隆著『小村寿太郎――近代日本外交の体現者――』 |
團藤 充己 |
108(566) |
|
中野聡著『東南アジア占領と日本人――帝国・日本の解体――』 |
上野美矢子 |
110(568) |
|
松原正毅著『カザフ遊牧民の移動 |
長沼 秀幸 |
111(569) |
|
文献目録 | ||
|
日本史Ⅱ |
113(571) |
|
|
会告 | ||
|
150(608) |
||
122編第3号
|
論文 | ||
|---|---|---|
|
日本古代の朝参制度と政務形態 |
志村佳名子 |
1(305) |
|
コラム 歴史の風 | ||
|
歴史学の醍醐味をどう伝えるか |
片山 剛 |
35(339) |
|
研究ノート | ||
|
宋代「対移」考――地方官監察・処分制度の実態―― |
宮崎 聖明 |
38(342) |
|
居留民団法の制定過程と中国の日本居留地 |
渡辺 千尋 |
62(366) |
|
書評 | ||
|
追塩千尋著『中世南部仏教の展開』 |
松尾 剛次 |
86(390) |
|
菊池一隆著『戦争と華僑 |
広中 一成 |
91(395) |
|
高畠純夫著『アンティフォンとその時代 |
前野 弘志 |
96(400) |
|
新刊紹介 | ||
|
木村茂光監修/歴史科学協議会編『戦後歴史学用語辞典』 |
佐藤 雄基 |
104(408) |
|
平川南著 『東北「海道」の古代史』 |
島崎 哲也 |
105(409) |
|
竹間芳明著『北陸の戦国時代と一揆』 |
長崎 健吾 |
106(410) |
|
黄自進著 『蒋介石と日本――友と敵のはざまで――』 |
野間 稔 |
108(412) |
|
早瀬晋三著『マンダラ国家から国民国家へ |
工藤 裕子 |
109(413) |
|
文献目録 | ||
|
日本史Ⅰ |
110(414) |
|
|
会告 | ||
|
|
103(407) |
|
122編第2号
|
論文 | ||
|---|---|---|
|
大正後期の松方正義と「元老制」の再編 |
荒船俊太郎 |
1(147) |
|
コラム 歴史の風 | ||
|
「東京裁判史観」を想う |
伊藤 隆 |
39(185) |
|
研究ノート | ||
|
15世紀後半におけるフィレンツェ毛織物会社のオスマン貿易 |
鴨野洋一郎 |
42(188) |
|
朝鮮政府の駐津大員の派遣(1883―1886) |
森 万佑子 |
66(212) |
|
書評 | ||
|
津野倫明著『長宗我部氏の研究』 |
平井 上総 |
87(233) |
|
城山智子著『大恐慌下の中国――市場・国家・世界経済――』 |
富澤 芳亜 |
94(240) |
|
黒川正剛著『魔女とメランコリー』 |
小林 繁子 |
101(247) |
|
樋口映美編『流動する<黒人>コミュニティ――アメリカ史を問う――』 |
大森 一輝 |
111(257) |
|
新刊紹介 | ||
|
野口実著 『武門源氏の血脈――為義から義経まで――』 |
木下 龍馬 |
117(263) |
|
土居聡朋・村井祐樹・山内治朋編『戰國遺文 瀬戸内水軍編』 |
山内 譲 |
118(264) |
|
金子拓編 『『信長記』と信長・秀吉の時代』 |
神田 裕理 |
119(265) |
|
安在邦夫著『自由民権運動史への招待』 |
松沢 裕作 |
120(266) |
|
濱本真実著『共生のイスラーム――ロシアの正教徒とムスリム――』 (イスラームを知る 5) |
清水由里子 |
121(267) |
|
文献目録 | ||
|
東洋史I |
123(269) |
|
|
会告 | ||
|
|
154(300) |
|
122編第1号
|
論文 | ||
|---|---|---|
|
宗教・帝国・「人道主義」――ウェズリアン・メソディスト宣教団と南部ベチュアナランド植民地化―― |
大澤 広晃 |
1(1) |
|
研究ノート | ||
|
宇垣軍縮の再検討――宇垣軍縮と第2次軍制改革―― |
髙杉 洋平 |
36(36) |
|
書評 | ||
|
遠藤珠紀著 『中世朝廷の官司制度』 |
本郷 恵子 |
61(61) |
|
藤村一郎著 『吉野作造の国際政治論 もう一つの大陸政策』 |
番定 賢治 |
69(69) |
|
河上麻由子著 『古代アジア世界の対外交渉と仏教』 |
藤原 崇人 |
77(77) |
|
鶴見太郎著 |
高尾千津子 |
85(85) |
|
第110回史学会大会報告 | ||
|
90(90) |
||
|
新刊紹介 | ||
|
西山良平・藤田勝也編著『平安京と貴族の住まい』 |
吉田 歓 |
114(114) |
|
埼玉県立嵐山史跡の博物館・葛飾区郷土と天文の博物館編 |
岩田 慎平 |
115(115) |
|
山崎信二著 |
市澤 泰峰 |
116(116) |
|
小名康之編 |
中西 啓太 |
117(117) |
|
神田豊隆著 |
樋口 真魚 |
118(118) |
|
塩川伸明・小松久男・沼野充義編 |
植田 暁 |
119(119) |
|
文献目録 | ||
|
西洋史I |
|
121(121) |
|
会告 | ||
|
|
143(143) |
|