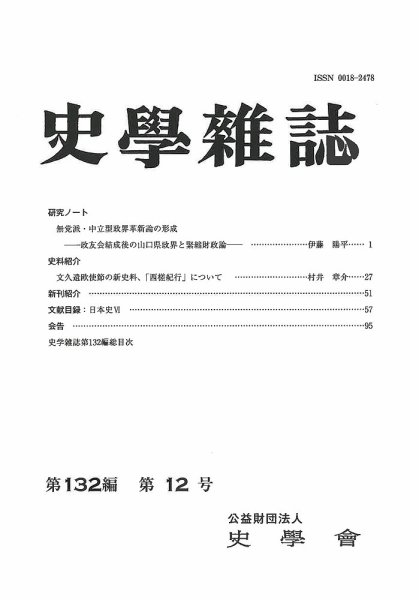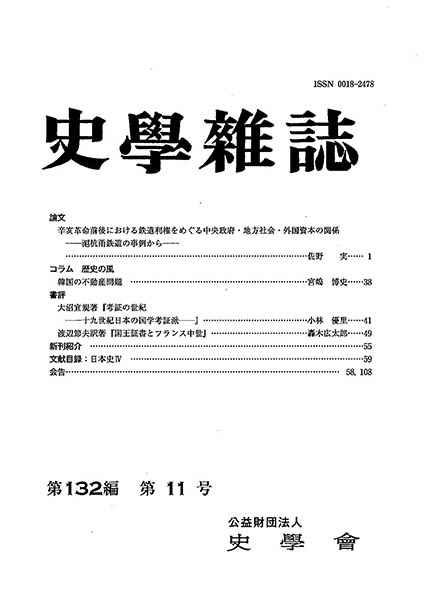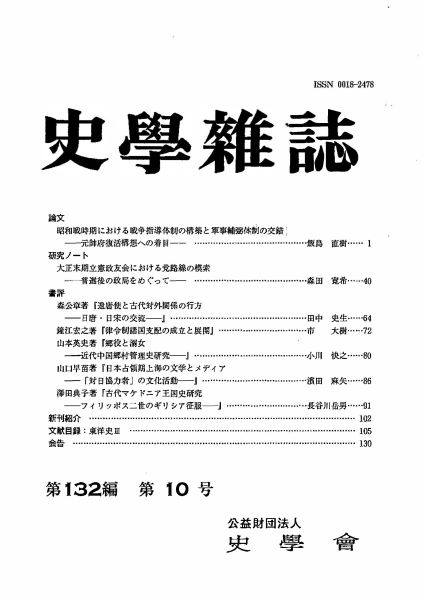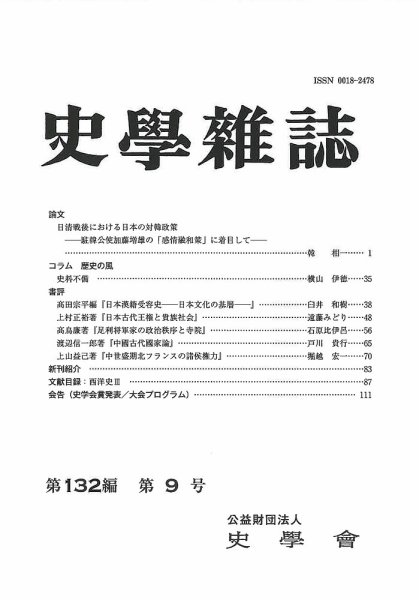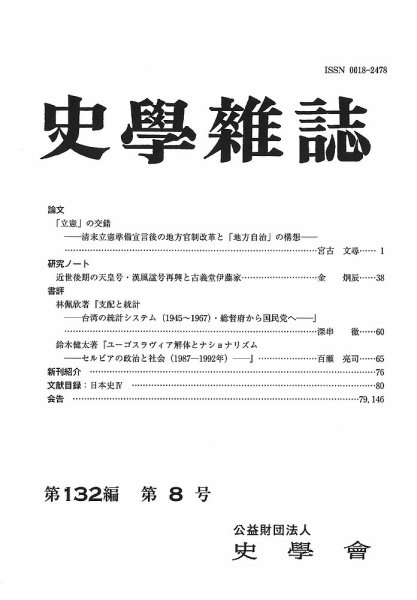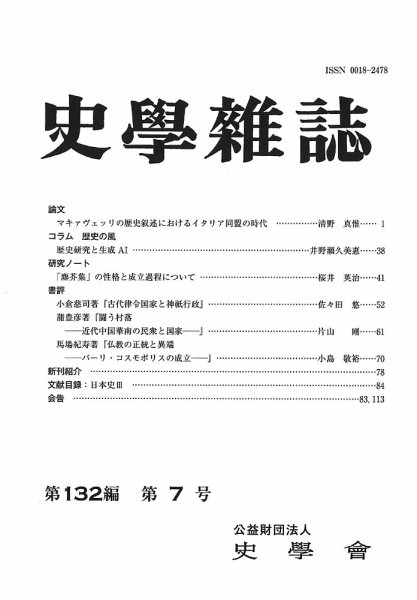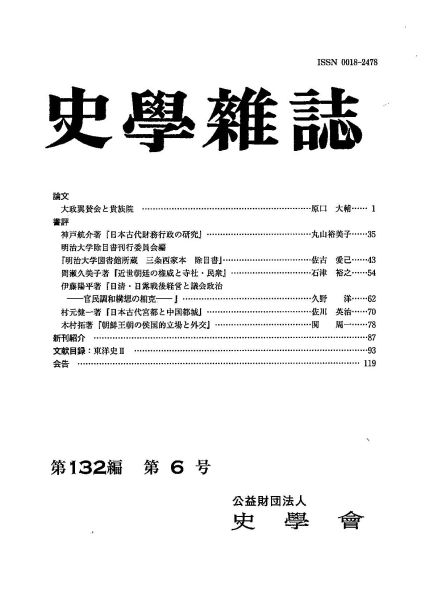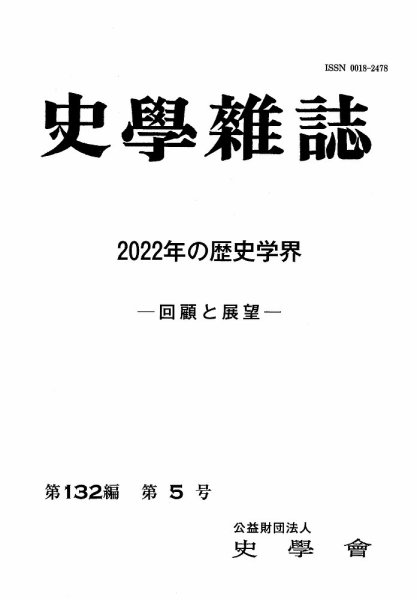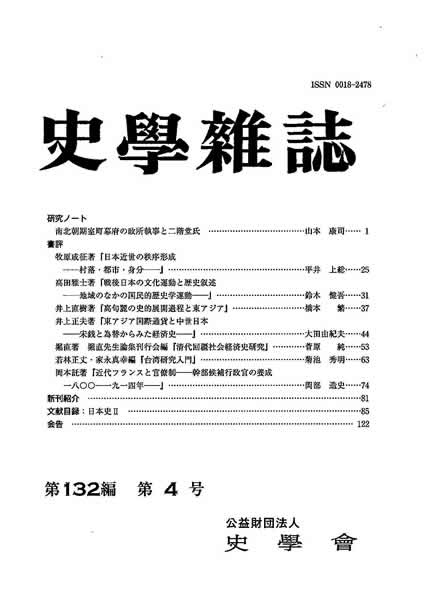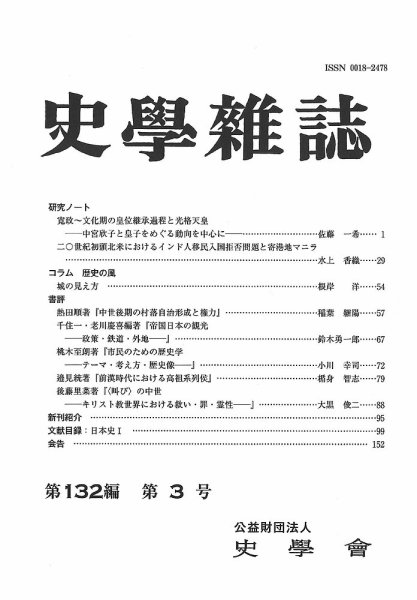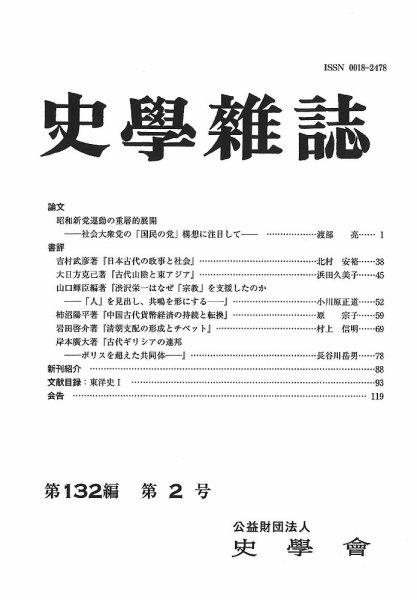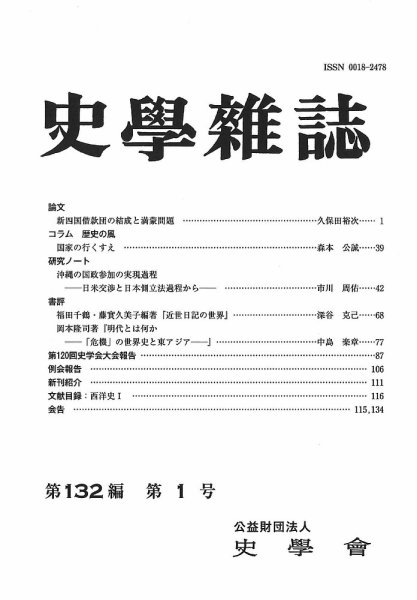史学雑誌目次 | バックナンバー 2023年 第132編
12号 11号 10号 9号 8号 7号 6号 5号 「回顧と展望」 4号 3号 2号 1号
132編第12号
|
研究ノート |
| |||
|---|---|---|---|---|
| 無党派・中立型政界革新論の形成 ――政友会結成後の山口県政界と緊縮財政論―― | |
伊藤 陽平 | 1(1707) | |
|
史料紹介 | ||||
|
文久遣欧使節の新史料、「西槎紀行」について |
村井 章介 | 27(1733) | ||
|
新刊紹介 | |||
|---|---|---|---|
| 森公章著『地方豪族の世界――古代日本をつくった30人――』(筑摩選書 0265) | 池田 純 | 51(1757) | |
| 倉本一宏・加藤友康・小倉慈司編『『小右記』と王朝時代』 | 大津 透 | 52(1758) | |
| 町田明広編『幕末維新史への招待』 | 藤澤 匡樹 | 54(1760) | |
| 川村邦光著『荒畑寒村――叛逆の文字とこしえに――』(ミネルヴァ日本評伝選) | 渡部 亮 | 55(1761) | |
|
文献目録 | |||
| 日本史Ⅵ | 57(1763) | ||
|
会告 | |||
| 95(1801) | |||
|
史学雑誌第132編総目次 | |||
132編 11号
|
書評 | |||
|---|---|---|---|
| 大沼宜規著『考証の世紀――十九世紀日本の国学考証派――』 | 小林 優里 | 41(1635) | |
| 渡辺節夫訳著『国王証書とフランス中世』(知泉学術叢書 19) | 轟木広太郎 | 49(1643) | |
|
新刊紹介 | |||
| 小笠原好彦著『古代宮都と地方官衙の造営』 | 新井 重行 | 55(1649) | |
| 東京大学史料編纂所編纂『大日本古記録 陽明文庫本 勘例下』 | 鈴木 蒼 | 56(1650) | |
| ディオロドス著、森谷公俊訳注『アレクサンドロス大王の歴史』 | 阿部 拓児 | 57(1651) | |
|
文献目録 | |||
| 日本史Ⅴ | 59(1653) | ||
|
会告 | |||
| 58(1652)、108(1702) | |||
132編第10号
|
論文 |
| |||
|---|---|---|---|---|
| 昭和戦時期における戦争指導体制の構築と軍事輔弼体制の交錯――元帥府復活構想への着目―― | |
飯島 直樹 | 1(1465) | |
|
研究ノート | ||||
|
大正末期立憲政友会における党路線の模索――普選後の政局をめぐって―― |
|
森田 寛希 | 40(1504) | |
|
書評 | |||
|---|---|---|---|
| 森公章著『遣唐使と古代対外関係の行方――日唐・日宋の交流――』 | 田中 史生 | 64(1528) | |
| 鐘江宏之著『律令制諸国支配の成立と展開』 | 市 大樹 | 72(1536) | |
| 山本英史著『郷役と溺女――近代中国郷村管理史研究――』(汲古叢書 169) | 小川 快之 | 80(1544) | |
| 山口早苗著『日本占領期上海の文学とメディア――「対日協力者」の文化活動――』 | 濱田 麻矢 | 86(1550) | |
| 澤田典子著『古代マケドニア王国史研究――フィリッポス二世のギリシア征服――』 | 長谷川岳男 | 91(1555) | |
|
新刊紹介 | |||
| 今津勝紀著『日本古代の環境と社会』 | 西本 哲也 | 102(1566) | |
| シュテフェン・パツォルト著 甚野尚志訳『封建制の多面鏡――「封」と「家臣制」の結合――』(刀水歴史全書 102) | 中川 友喜 | 103(1567) | |
|
文献目録 | |||
| 東洋史Ⅲ | 105(1569) | ||
|
会告 | |||
| 130(1594) | |||
132編第9号
|
書評 | |||
|---|---|---|---|
| 髙田宗平編『日本漢籍受容史――日本文化の基層――』 | 臼井 和樹 | 38(1380) | |
| 上村正裕著『日本古代王権と貴族社会』 | 遠藤みどり | 48(1390) | |
| 髙鳥廉著『足利将軍家の政治秩序と寺院』 | 石原比伊呂 | 56(1398) | |
| 渡辺信一郎著『中國古代國家論』(汲古叢書 175) | 戸川 貴行 | 65(1407) | |
| 上山益己著『中世盛期北フランスの諸侯権力』 | 堀越 宏一 | 70(1412) | |
|
新刊紹介 | |||
| 吉村武彦ほか編『墨書土器と文字瓦――出土文字史料の研究――』 | 榊 佳子 | 83(1425) | |
| 菅原慶郎著『近世海産物の生産と流通――北方世界からのコンブ・俵物貿易――』 | 竹澤 翔 | 84(1426) | |
| 今村薫編『中央アジア牧畜社会――人・動物・交錯・移動――』 | 大野 和馬 | 85(1427) | |
|
文献目録 | |||
| 西洋史Ⅲ | 87(1429) | ||
|
会告 | |||
| 111(1453) | |||
132編第8号
|
書評 | |||
|---|---|---|---|
| 林佩欣著『支配と統計――台湾の統計システム(1945~1967)・総督府から国民党へ――』 | 深串 徹 | 60(1256) | |
| 鈴木健太著『ユーゴスラヴィア解体とナショナリズム ――セルビアの政治と社会(1987―1992年)――』 | 百瀬 亮司 | 65(1261) | |
|
新刊紹介 | |||
| 小川幸司責任編集、島田竜登編集協力『岩波講座 世界歴史 第11巻 構造化される世界 14~19世紀』 | 溝渕 智咲 | 76(1272) | |
| 倉本一宏著『平氏――公家の盛衰、武家の興亡――』(中公新書2705) | 室伏 奏楽 | 77(1273) | |
| 角鹿尚計著『橋本佐内――人間自ら適用の士有り――』(ミネルヴァ日本評伝選) | 三谷 博 | 78(1274) | |
|
文献目録 | |||
| 日本史Ⅳ | 80(1276) | ||
|
会告 | |||
| 79(1275),146(1342) | |||
132編第7号
|
論文 |
| |||
|---|---|---|---|---|
|
マキァヴェッリの歴史叙述におけるイタリア同盟の時代 |
|
清野 真惟 | 1(1083) | |
|
コラム 歴史の風 | ||||
|
歴史研究と生成AI |
井野瀬久美惠 | 38(1120) | ||
|
研究ノート | ||||
|
「塵芥集」の性格と成立過程について |
|
桜井 英治 | 41(1123) | |
|
書評 | |||
|---|---|---|---|
| 小倉慈司著『古代律令国家と神祇行政』(同成社古代史選書 38) | 佐々田 悠 | 52(1134) | |
| 蒲豊彦著『闘う村落――近代中国華南の民衆と国家――』 | 片山 剛 | 61(1143) | |
| 馬場紀寿著『仏教の正統と異端――パーリ・コスモポリスの成立――』 | 小島 敬裕 | 70(1152) | |
|
新刊紹介 | |||
| 小澤実・佐藤雄基編『史学科の比較史――歴史学の制度化と近代日本――』 | 松岡 昌和 | 78(1160) | |
| 鎌倉佐保・木村茂光・高木徳郎編『荘園研究の論点と展望――中世史を学ぶ人のために――』 | 朝比奈 新 | 79(1161) | |
| 大藤修著『近世庶民社会論――生老死・「家」・性差――』 | 西村慎太郎 | 80(1162) | |
| 谷口眞子著『葉隠<武士道>の史的研究』 | 山田 拓実 | 81(1163) | |
| アフメト・シェフィク・ミドハト著、アリ・ハイダル・ミドハト編、佐々木紳訳『ミドハト・パシャ自伝――近代オスマン帝国改革実録――』 | 永島 育 | 82(1164) | |
|
文献目録 | |||
| 日本史Ⅲ | 84(1166) | ||
|
会告 | |||
| 83(1165),113(1195) | |||
132編第6号
|
書評 | |||
|---|---|---|---|
| 神戸航介著『日本古代財務行政の研究』 | 丸山裕美子 | 35(995) | |
| 明治大学除目書刊行委員会編『明治大学図書館所蔵 三条西家本 除目書』 | 佐古 愛己 | 43(1003) | |
| 間瀬久美子著『近世朝廷の権威と寺社・民衆』 | 石津 裕之 | 54(1014) | |
| 伊藤陽平著『日清・日露戦後経営と議会政治――官民調和構想の相克――』 | 久野 洋 | 62(1022) | |
| 村元健一著『日本古代宮都と中国都城』 | 佐川 英治 | 70(1030) | |
| 木村拓著『朝鮮王朝の侯国的立場と外交』 | 関 周一 | 78(1038) | |
|
新刊紹介 | |||
| 小川幸司責任編集『岩波講座世界歴史 第1巻 世界史とは何か」 | 田中 雅人 | 87(1047) | |
| 深井雅海著『江戸城御殿の構造と儀礼の研究――空間に示される権威と秩序―― | 小宮山敏和 | 88(1048) | |
| 寺内由佳著『近世の衣料品流通と商人――地方都市宇都宮を中心に――』(山川歴史モノグラフ 42) | 山本 一夫 | 89(1049) | |
| 中村元哉・森川裕貫・関智英・家永真幸著『概説 中華圏の戦後史』 | 倉田 徹 | 90(1050) | |
| ジュディス・ヘリン著、井上浩一訳『ラヴェンナ――ヨーロッパを生んだ帝都の歴史――』 | 長澤 咲耶 | 91(1051) | |
|
文献目録 | |||
| 東洋史Ⅱ | 93(1053) | ||
|
会告 | |||
| 119(1079) | |||
132編第5号 回顧と展望
|
総説 |
| ||
|---|---|---|---|
|
大津 透 |
1(535) |
||
|
歴史理論 | |||
|
佐藤 公美 |
6(540) |
||
|
日本史 | |||
|---|---|---|---|
|
考 古 |
尾田 識好 上條 信彦 齋藤 瑞穂 木村 理 湯沢 丈 |
11(545) |
|
|
古 代 |
今津 勝紀 古市 晃 毛利 憲一 村上 菜菜 竹内 亮 黒羽 亮太 手嶋 大侑 山口 えり 江草 宣友 佐藤有希子 |
38(572) |
|
|
中 世 |
早島 大祐 山田 徹 生駒 孝臣 小原 嘉記 松永 和浩 久水 俊和 佐々木倫朗 西島 太郎 大河内 勇介 坪井 剛 大田壮一郎 安藤 弥 榎本 渉 梅沢 恵 |
76(610) |
|
| 近 世 | 野村 玄 馬部 隆弘 尾﨑 真理 綱澤 広貴 佐藤 一希 後藤 敦史 上田 長生 東野 将伸 平田 良行 糸川 風太 片山 早紀 古林小百合 宮崎 もも |
114(648) |
|
|
近現代 |
白木沢旭児 武藤三代平 川口 暁弘 木村 聡 井上 敬介 加藤 絢子 久保田裕次 花田 智之 内藤 隆夫 満薗 勇 板垣 暁 中川 未来 加藤 祐介 本庄 十喜 大谷 伸治 及川 琢英 春原 史寛 |
152(686) |
|
|
東アジア | |||
|
中 国 |
|||
|
殷・周・春秋 |
長澤 文彩 |
199(733) |
|
|
戦国・秦漢 |
渡邉 英幸 |
205(739) |
|
|
魏晋南北朝 |
小野 響 |
212(746) |
|
|
隋・唐 |
竹内 洋介 |
217(751) |
|
|
五代・宋・元 |
塩 卓悟 |
224(758) |
|
|
明・清 |
岩本真利絵 |
231(765) |
|
|
近現代 |
佐藤 淳平 菅野 智博 |
237(771) |
|
|
台湾 |
松葉 隼 |
254(788) |
|
|
朝 鮮 |
呉 吉煥 田中 俊光 閔 東曄 |
257(791) |
|
|
内陸アジア | ||
|---|---|---|
|
宮本 亮一 植田 暁 |
267(801) |
|
|
東南アジア | ||
|
大泉さやか |
278(812) |
|
|
南アジア | ||
|
井田 克征 水澤 純人 |
286(820) |
|
|
西アジア・北アフリカ | ||
|
竹野内 恵太 三木 健裕 岩本 佳子 徳永 佳晃 |
295(829) |
|
|
アフリカ | ||
|
中尾 世治 |
313(847) |
|
|
ヨーロッパ | |||
|---|---|---|---|
|
古 代 |
|||
|
ギリシア |
周藤 芳幸 |
317(851) |
|
|
ローマ |
福山 佑子 |
321(855) |
|
|
中 世 |
|||
|
一般 |
山本 成生 |
325(859) |
|
|
西欧・南欧 |
山本 成生 |
326(860) |
|
|
中東欧・北欧 |
三浦 麻美 |
331(865) |
|
|
イギリス |
荒木 洋育 |
334(868) |
|
|
ロシア・ビザンツ |
浜田 華練 |
338(872) |
|
|
近 代 |
|||
|
一般 |
坂下 史 |
341(875) |
|
|
イギリス |
穴井 佑 水田 大紀 |
343(877) |
|
|
フランス |
福島 知己 |
350(884) |
|
|
ドイツ・スイス・ネーデルラント |
前田 充洋 |
357(891) |
|
|
ロシア・東欧・北欧 |
伊藤 順二 |
363(897) |
|
|
近現代南欧 |
内村 俊太 |
368(902) |
|
|
現 代 |
|||
|
一般 |
村田奈々子 |
371(905) |
|
|
イギリス |
水谷 智 |
374(908) |
|
|
フランス |
齊藤 佳史 |
378(912) |
|
|
ドイツ・スイス・ネーデルラント |
福永美和子 |
382(916) |
|
|
ロシア・東欧・北欧 |
加藤 久子 |
389(923) |
|
|
アメリカ | |||
|
北アメリカ |
鈴木 周太郎 南川 文里 |
396(930) |
|
|
ラテン・アメリカ |
佐藤 正樹 |
405(939) |
|
|
執筆者紹介 | |||
|
408(942) |
|||
|
編集後記 | |||
|
410(944) |
|||
|
文献目録 | |||
|
西洋史II |
411(945) |
||
|
会告 | |||
|
426(960) |
|||
132編第4号
|
書評 | |||
|---|---|---|---|
| 牧原成征著『日本近世の秩序形成――村落・都市・身分――』 | 平井 上総 | 25(437) | |
| 高田雅士著『戦後日本の文化運動と歴史叙述――地域のなかの国民的歴史学運動――』 | 鈴木 健吾 | 31(443) | |
| 井上直樹著『高句麗の史的展開過程と東アジア』 | 橋本 繁 | 37(449) | |
| 井上正夫著『東アジア国際通貨と中世日本――宋銭と為替からみた経済史――』 | 大田由紀夫 | 44(456) | |
| 堀直著 堀直先生論集刊行会編『清代回疆社会経済史研究』 | 菅原 純 | 53(465) | |
| 若林正丈・家永真幸編『台湾研究入門』 | 菊池 秀明 | 63(475) | |
| 岡本託著『近代フランスと官僚制――幹部候補行政官の養成1800―1914年――』 | 岡部 造史 | 74(486) | |
|
新刊紹介 | |||
| 高橋勝浩編『出淵勝次日記』 | 大窪 有太 | 81(493) | |
| 平澤歩著『漢代経学に於ける五行説の変遷』 | 三浦 雄城 | 82(494) | |
| ジョン・H.アーノルド著、図師宣忠・赤江雄一訳『中世史とは何か』 | 弓岡 弘樹 | 83(495) | |
|
文献目録 | |||
| 日本史Ⅱ | 85(497) | ||
|
会告 | |||
| 122(534) | |||
132編第3号
|
研究ノート |
| |||
|---|---|---|---|---|
|
寛政~文化期の皇位継承過程と光格天皇――中宮欣子と皇子をめぐる動向を中心に―― |
|
佐藤 一希 |
1(259) |
|
|
二〇世紀初頭北米におけるインド人移民入国拒否問題と寄港地マニラ |
|
水上 香織 | 29(287) | |
|
コラム 歴史の風 | ||||
|
城の見え方 |
根岸 洋 | 54(312) | ||
|
書評 | |||
|---|---|---|---|
| 熱田順著『中世後期の村落自治形成と権力』 | 稲葉 継陽 | 57(315) | |
| 千住一・老川慶喜編著『帝国日本の観光――政策・鉄道・外地――』 | 鈴木勇一郎 | 67(325) | |
| 桃木至朗著『市民のための歴史学――テーマ・考え方・歴史像――』 | 小川 幸司 | 72(330) | |
| 邉見統著『前漢時代における高祖系列侯』(汲古叢書172) | 楯身 智志 | 79(337) | |
| 後藤里菜著『〈叫び〉の中世――キリスト教世界における救い・罪・霊性――』 | 大黒 俊二 | 88(346) | |
|
新刊紹介 | |||
| 藤本健太郎著『長崎偉人伝 松田源五郎』 | 松本 洋幸 | 95(353) | |
| 永原陽子責任編集『岩波講座世界歴史 18 アフリカ諸地域 ~20世紀』 | 古川 哲史 | 96(354) | |
| デイヴィッド・アブラフィア著、高山博監訳、佐藤昇・藤崎衛・田瀬望訳『地中海と人間――原始・古代から現代まで―― Ⅰ 原始・古代から14世紀 Ⅱ 14世紀から現代』 | 藤田 風花 | 97(355) | |
|
文献目録 | |||
| 日本史Ⅰ | 99(357) | ||
|
会告 | |||
| 152(410) | |||
132編第2号
|
書評 | |||
|---|---|---|---|
| 吉村武彦著『日本古代の政事と社会』 | 北村 安裕 | 38(174) | |
| 大日方克己著『古代山陰と東アジア』(同成社古代史選書 42) | 浜田久美子 | 45(181) | |
| 山口輝臣編著『渋沢栄一はなぜ「宗教」を支援したのか――「人」を見出し、共鳴を形にする――』(渋沢栄一と「フィランソロピー」 7) | 小川原正道 | 52(188) | |
| 柿沼陽平著『中国古代貨幣経済の持続と転換』(汲古叢書 148) | 原 宗子 | 59(194) | |
| 岩田啓介著『清朝支配の形成とチベット』(汲古叢書 170) | 村上 信明 | 69(205) | |
| 岸本廣大著『古代ギリシアの連邦――ポリスを超えた共同体――』 | 長谷川岳男 | 78(214) | |
|
新刊紹介 | |||
| 下坂 守著『中近世祇園社の研究――祇園祭千百五十年記念――』 | 藤原 重雄 | 88(224) | |
| 安堵町歴史民俗資料館古文書解読グループ編『奈良奉行所同心神武天皇陵補修日記』 | 佐竹 朋子 | 89(225) | |
| 橋場弦著『古代ギリシアの民主政』(岩波新書 1943) | 内田 康太 | 90(226) | |
| フロセル・サバテ著、阿部俊大監訳『アラゴン連合王国の歴史――中世後期ヨーロッパの一政治モデル――』(世界歴史叢書) | 清野 真惟 | 91(227) | |
|
文献目録 | |||
| 東洋史Ⅰ | 93(229) | ||
|
会告 | |||
| 119(255) | |||
132編第1号
|
論文 |
| |||
|---|---|---|---|---|
|
新四国借款団の結成と満蒙問題 |
|
久保田裕次 |
1(1) |
|
|
コラム 歴史の風 | ||||
|
国家の行くすえ |
森本 公誠 | 39(39) | ||
|
研究ノート | ||||
|
沖縄の国政参加の実現過程――日米交渉と日本側立法過程から―― |
|
市川 周佑 | 42(42) | |
|
書評 | |||
|---|---|---|---|
| 福田千鶴・藤實久美子編著『近世日記の世界』(史料で読み解く日本史 4) | 深谷 克己 | 68(68) | |
| 岡本隆司著『明代とは何か――「危機」の世界史と東アジア――』 | 中島 楽章 | 77(77) | |
|
第120回史学会大会報告 | |||
| 87(87) | |||
|
例会報告 | |||
| 106(106) | |||
|
新刊紹介 | |||
| 吉村武彦・吉川真司・川尻秋生編『国風文化――貴族社会のなかの「唐」と「和」――』(シリーズ 古代史をひらく) | 中島 皓輝 | 111(111) | |
| 伊藤喜良著『動乱と王権――南北朝・室町時代――』(高志書院選書 13) | 坂井 武尊 | 112(112) | |
| 川島真・岩谷將編『日中戦争研究の現在――歴史と歴史認識問題――』 | 吉井 文美 | 113(113) | |
| アイム・ブルスティン著、田中正人訳『創られたサン=キュロット――革命期パリへの眼差し――』(叢書・ウニベルシタス 1145) | 楠田 悠貴 | 114(114) | |
|
文献目録 | |||
| 西洋史Ⅰ | 116(116) | ||
|
会告 | |||
| 115,134(115,134) | |||